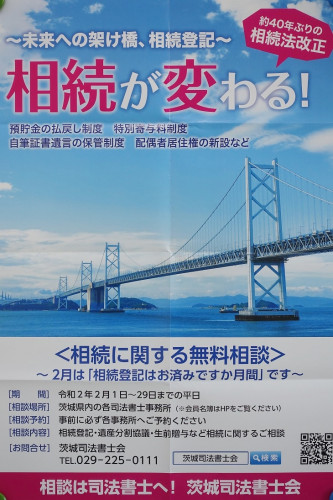インフォメーション
R2.2.19 真壁のひなまつり
お客さん宅で打ち合わせということで、真壁町に行きました。
以前に「真壁のひな祭り」という話を聞いたことがあったので、どんなものかと思っていました。
折角だったので町中を散策してみました。
皆さんの自宅とかお店にそれぞれの家で代々伝わっているひな人形などを飾って、町全体でひな祭りをしようという感じでした。
「真壁のひなまつりマップ」があって、それを見る限り数百件のお宅でひな人形などが飾ってありそうです。
下の写真は、普通の民家の玄関に飾られたもので、江戸時代から明治、大正、昭和とそれぞれの時代に作られたひな人形か飾られていました。どれもきれいで、江戸時代のひな人形がきれいに保管されていることに驚きました。
最後の写真は、おまけです。
真壁には、風力発電所があるらしいです。めずらしいので記念に撮りました。
写真では、プロペラ部分の動いている感が伝わってきませんが、結構な速さで回転していました。
江戸時代から令和の時代までを見た感じでした。
R2.2.4 牛久市社会福祉協議会 研修会「民事信託制度について」
R2.2.4(火)午後2時から午後3時過ぎまで 牛久市社会福祉協議会 (ボランティア・市民活動センター 牛久市中央三丁目)で民事信託制度について研修会を担当いたしました。
同協議会からのご依頼では「民事信託制度について」ということだったのですが、受講される方が同協議会の「心配ごと相談事業」の相談員ということだったので、福祉型の信託をメインにしてお話をさせていただきました。
持ち時間が1時間ということで、先ずは全体像を理解していただいて、その後、「親なき後」「認知症高齢者のための信託」など福祉型の信託についてお話をいたしました。
中には信託の話を初めて聞くという方もいらしたので、どこまで説明しようかと戸惑う面もありましたが、その心配も杞憂に終わり、受講者から質問がたくさん出て、話がどんどんと突っ込んだ内容になりました。受託者に所有権を移したら受託者は何でもできるのではないか?とか、受託者は財産を管理するのが仕事だとしても、良い人だという性善説に立ちすぎではないのか、と。
このような方がキッチリと法律を勉強すると理解が速いのだろうなと感心しきりでした。
質問が多く出たということもあり、持ち時間を大幅にオーバーしてしまいました。受講者には申し訳ないとは思いますが、個人的にはとても楽しかったです。
次回も期待したいと思います。
2月は「相続登記はお済みですか」月間(無料相談)のお知らせ 2020
約40年ぶりに相続法が改正されます。これにより相続が変わります。
たとえば、去年の1月からは自筆証書遺言が書き易くなっていますし、同じく去年の7月から新しい預貯金の払戻制度が運用されています。
また、今年の4月からは「配偶者居住権」が新設され、7月からは「自筆証書遺言の保管制度」が開始されます。
今年も日本司法書士会連合会、茨城司法書士会では、2月を「相続登記はお済ですか月間」と銘打って、相続、贈与、遺言などについて、各司法書士事務所での無料相談を開催します。
実施要領は下記のとおりです。各司法書士事務所にあらかじめご予約の上、ご利用ください。
ご不明な点は、茨城司法書士会 TEL 029-225-0111 にお問い合わせください。
年末・年始の休業のお知らせ2019
年末年始につきましては、令和元年12月28日(土)から令和2年1月5日(日)まで休業とさせていただきます。
新年は令和2年1月6日(月)から平常通り営業いたします。
皆様、本年も大変お世話になり、ありがとうございました。
そして、良いお年をお迎えください。